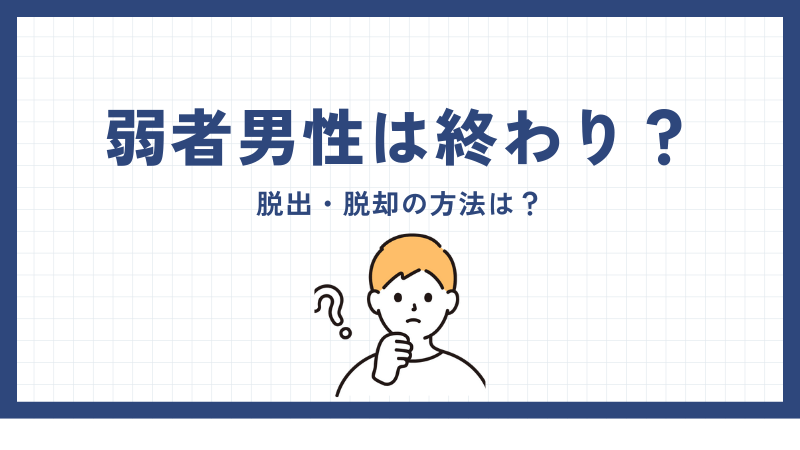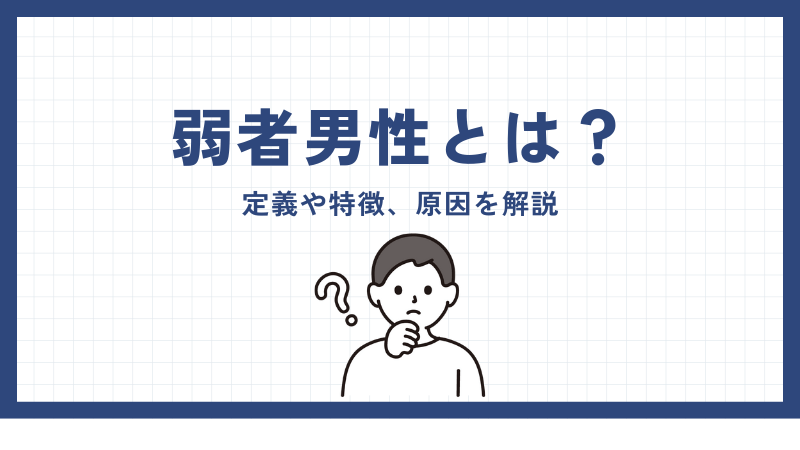
近年、弱者男性という言葉を耳にすることが多くなりました。
差別的な使われることが多い言葉ではありますが、どのような意味があり、どのような人が弱者男性に該当するのか気になった方は多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、弱者男性の定義や特徴、弱者に陥る原因について解説します。
弱者男性から脱却する方法についても紹介するので、興味のある方はぜひご覧ください。
弱者男性とはどんな意味?
「弱者男性」は2010年代以降、日本社会で頻繁に使用されるようになった言葉です。
主に経済面や社会面において、複数の弱者要素を持つ男性を指す言葉として使用されています。
- 非正規雇用で低収入
- 障がいを持っている
- コミュ障で社会から孤立
などなど、社会的不利益を被っている男性を指すことが一般的です。
弱者男性の問題点は、一度弱者の立場に陥ってしまうと負のスパイラルにはまりやすく、容易に抜け出せないという点でしょう。
例えば、経済的余裕のない貧困家庭に生まれた場合、十分な教育を受けられず低収入な仕事に就きやすくなります。
低収入から脱却するために転職しようと思っても、高収入の仕事はそれ相応の資格を求められたり、キャリア年数が必要がったりしますよね。
転職に手こずっているとそのまま年齢を重ねてしまい、さらに転職に不利になるケースも珍しくありません。
これが弱者男性の負のスパイラルです。
弱者男性に定義はある?
「弱者男性」という言葉に、学術的・法的に確立された明確な定義は存在しません。
そのため、現在は前述した”社会的不利益を被っている男性”を弱者男性と呼んでいます。
しかし、SNSでは「自分が気に食わない男性」を弱者男性と読んだり、いわゆるレスバトルでの悪口として利用されたりしているのが現状です。
日本における弱者男性の割合
小樽大学の池田真介教授によると、日本には1500万人の弱者男性がいるとされています。
この数値が正しいと仮定した場合、日本男性の4人に1人が弱者男性になる計算です。
弱者男性に該当する人の特徴

弱者男性に該当する人の特徴は、主に9個あります。
低学歴
学歴はその人の能力を判断する重要な指標であり、就職に大きな影響を与えます。
高学歴であれば職業選択に幅が利きますが、低学歴だと自分が希望する職業に就くことが難しくなるでしょう。
その結果、3K(きつい、汚い、危険)と呼ばれる仕事や低賃金の仕事に就きやすくなり、経済的な余裕がなくなってしまいがちです。
低収入
低収入は弱者男性の代表的な特徴の1つで、前述した低学歴が低収入な仕事に繋がっています。
もちろん、高学歴でもすべての人が高収入の仕事に就けているわけではありませんし、低学歴だから絶対に低収入な仕事に就くわけでもありません。
ただ、学歴と年収には相関関係があることが分かっており、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、高卒と大卒では年収に約100万円の差があることが分かっています。
非正規や派遣
非正規雇用や派遣社員として働いている人は、雇用が安定しないので低収入になりやすいことが特徴です。
また、裁量の大きい職業を任せてもらえないため、キャリアを積むことができずスキルアップも見込めません。
容姿が優れていない
外見的特徴は、社会生活における第一印象を左右する重要な要素です。
極論、容姿が優れていれば女性からモテますが、ブサイクだと女性からモテません。
男性自身が容姿の悪さを自覚している場合、自己肯定感が低くなり対人関係における自信の喪失にも繋がってしまいます。
その結果、積極的にコミュニケーションを取らなくなることもあるので、社会的に孤立してしまうことも珍しくありません。
パートナーががいない
男性にとって、パートナーの有無は幸福度に直結する要素です。
日本版総合的社会調査によると、独身女性と比較して独身男性は幸福度が低いことが分かっています。
また、低収入によって結婚ができなかったり、容姿が悪くモテなったりすることでパートナーが見つからないこともあるので、他の弱者要素と相関関係があると言えるでしょう。
障がいを持っている
障がいを持っている人は男女を問わず、支援を受けるべき社会的弱者の立場にあります。
障がいの重さによっては働き口を見つけにくく、社会復帰も難しくなるでしょう。
趣味がサブカル系
アニメやゲーム、Vtuberなどがサブカル系の趣味に該当します。
誤解のないように言っておくと、サブカル系の趣味だからといって弱者というわけではありません。
ただ、サブカル系の趣味は現実逃避の手段になりやすくなったり、容姿に対して無頓着になりやすい傾向にあったりなど、弱者要素に繋がりやすくなります。
カードゲーム屋に集まる人だったり、オタク趣味で集まった人のオフ会だったりを想像すれば分かりやすいのではないでしょうか。
趣味に没頭することも幸せの形の1つではありますが、そういった趣味に没頭する人に弱者男性が多い傾向にあります。
コミュ障
ウィキペディアでは、コミュ障の人も弱者男性に含まれると記載されています。
コミュ障の人は他者とのコミュニケーションを避けることが多く、社会からも孤立しやすいので、結果として弱者という立場に陥りやすいです。
また、物事に対して受動的・受け身の姿勢を取りやすいので、自身が適応できる就職先が限られたり、職場での昇進チャンスを逃すリスクも高くなるでしょう。
実家暮らし
経済的な自立の困難さから、親元での生活を継続せざるを得ないケースが存在します。
自分から実家暮らしをしている方もいますが、社会的な自立が遅れたり、新しい人間関係の構築機会を逃したりする可能性が高いです。
現状、男性の実家暮らしは女性にネガティブな印象を与えやすく、恋愛や結婚の機会を逃す可能も高くなってしまうでしょう。
弱者男性に陥ってしまう原因

ここからは、弱者男性に陥ってしまう原因について紹介します。
家庭環境
家庭環境によっては、生まれながらにして弱者の立場に陥ってしまいます。
例えば、裕福な家庭に生まれた人は高い水準の教育を受ける機会に恵まれ、一般的に高学歴に該当するような大学を卒業する確率が高くなるでしょう。
実際、2020年度に東京大学が実施した「学生生活実態調査」によると、東大生の親の42.5%が年収1050万以上というデータも出ています。
その一方で貧困家庭に生まれた人は、十分な教育を受けられないことが多く、経済的なハンディキャップを埋められず低収入な職業に就職することになるケースも珍しくありません。
つまり、生まれながらにして「強者」と「弱者」に分けられるということですね。
リンク:弱者男性が自己責任と言い切れない3つの理由
両親からの遺伝
両親からの遺伝も弱者男性に陥る要因の1つです。
「さすがに責任転嫁じゃない?」と思われるかもしれませんが、親から受け継ぐ”才能”というのは人生に大きな影響を及ぼします。
行動遺伝学の研究では才能の約50%は遺伝で決まることが分かっており、残りの50%は前述した家庭環境で決まると言われているんです。
極論、貧困家庭で才能のない両親から生まれた場合、多大な苦労に見舞われる可能性が高いと言えるでしょう。
これに対して「弱者男性になるのは本人の努力不足」と言ってくる人もいると思います。
ただ、ミシガン州立大学とテキサス大学の共同実験によって、”努力遺伝子”も両親から遺伝し、努力できるかは生まれながらにして決まってしまうことが判明しました。
参考文献:The genetics of music accomplishment: evidence for gene-environment correlation and interaction
以上のことから、両親の遺伝は弱者男性に陥る大きな原因になっていると言えます。
病気や怪我
健康上の問題は、個人の社会的立場を大きく変える可能性がある重要な要素です。
運次第で誰でも病気や怪我を負う可能性があり、場合によっては障がいが残ってしまうこともあるでしょう。
障がいを持つ人は、支援が必要な社会的弱者の立場に置かれるので、弱者男性に陥る要因として決して馬鹿にできません。
弱者男性になると脱却が難しい
現代の競争社会において、一度「弱者」の立場に陥ってしまうと、負のスパイラルのはまってしまいます。
特に弱者男性は男性に求められる「男らしさ」が足を引っ張り、社会的な援助が必要な立場であるにも関わらず、生活保護などの制度に申し込まないケースが多いです。
その結果、生活の質が大きく低下しても助けを求める意識が形成されず、弱者から脱却できなくなることも珍しくありません。
もし経済的に苦しくなったときは、素直に生活保護や雇用・労働求職者支援制度を利用しましょう。
主な弱者男性からの脱却方法については、以下の記事をご覧ください。